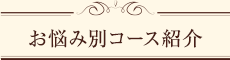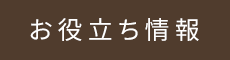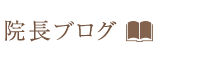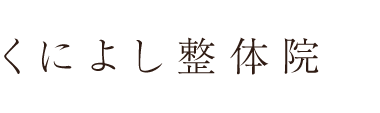こんにちは、宮崎県都城市で整体院をしておりますくによし整体院です。みなさんはこんなことに悩んだりしていないでしょうか?
・腕をあげると痛い
・日中は大丈夫だけど寝ている時に疼いたり寝返りの時に痛い
・腕は挙げれるが挙げる途中が痛い
・髪を洗ったり帯を結ぶのが辛い
・肩に痛みに伴って頭痛もある
・肩から腕にかけてしびれや痛みがある
上記のような症状で悩まれている方今ご自身の肩に何が起きているのか心配ではないですか?今回はそんな肩の痛みについてお話をしていきます。とりあえず治療を受けたい方は↓をクリックしてご予約お願いします。

肩の解剖
肩関節は股関節や膝関節などのほかの関節と比べて、可動域が格段に広く様々な方向に腕を動かすことができるようになっているので、身体の中でもっとも肩関節は複雑な構造をしています。なので、他の関節で見られるような骨格や靭帯による安定性が肩部分には欠けており、肩関節(肩甲上腕関節)の安定性は周囲の筋肉に頼る形となりますので、本質的に不安定であるのは変わりません。肩鎖関節は肩甲骨と鎖骨で構成される関節で、肩の位置を保つの役割と上肢を胴体に繋ぎとめる重要な役割を担っています。腕の動きに対して肩甲骨と共に上下左右・回旋の動きを起こします。
肩の傷害は、野球などのボールの投球動作などで直接的な負荷が加わったり、転倒などの上肢へのストレスが腕を通じて加わることで起こる二つの種類があります。
肩の動きに関わる骨
・肩甲骨
平らな形状をしていて、身体の胸部の背面少し外側寄りに位置しており、肩甲骨の後面を上下に分けるよう際立った隆起を肩甲棘と呼びます。その肩甲棘の外側先端部分の突起の部分を肩峰と呼びます。肩峰の下に、カップ状のくぼみ部分を関節窩と呼び肩関節になります。
・上腕骨
上肢のなかで最も長くて大きい骨になります。遠位では上腕骨と橈骨と尺骨で肘関節を形成しているが、近位では肩甲骨と上腕骨で肩関節を形成しています。近位部分は関節の面が丸くなっており上腕骨頭になっており、これが肩甲骨の関節窩にはまります。
鎖骨(さこつ)
上肢を胴体と繋げる役割があり、力の伝達に関与します。鎖骨は肩関節の色々な動きをサポートしてくれ、さらに腕の重さを胸郭に分散させる機能を担っています。これにより、上肢の運動や負荷に対する耐性が上がります。
肩の動きに関わる筋肉
僧帽筋(そうぼうきん)
僧帽筋は、頭の後ろから肩・背中の上部にかけて広がる大きな筋肉で3つに別れています。僧帽筋上部・中部・下部に分かれており、肩甲骨の上下の移動や肩甲骨を背骨に寄せる動作を行うことができます。
三角筋(さんかくきん)
三角筋は、前三角筋、中三角筋、後三角筋といった三つの部分に分けられます。肩関節の安定性と動きの範囲を広げるためのサポートをしてくれます。
広背筋(こうはいきん)
広背筋は、腕を内側や後ろに動かす、内側方向に捻るなどの動きをサポートしてくれます。肩以外の他にも骨盤の動きや呼吸、肩甲骨の固定にも関与します。背中に付きながらも腕の動きに広く関わるという点が特徴です。
菱形筋(りょうけいきん)
菱形筋は背骨と肩甲骨をつなぐ筋肉で、役割は左右の肩甲骨を背骨に近づける働きがあり、胸をはる姿勢をする時などで使う筋肉です。
棘上筋(きょくじょうきん)
棘上筋は肩甲骨側から上腕骨に付着しており、腕を横に持ちあげる役割を果たします。
棘下筋(きょっかきん)
棘下筋は肩甲骨側から上腕骨に付着しており、腕を外向きにひねる役割を果たす。
小円筋(しょうえんきん)
小円筋は肩甲骨の外側から上腕骨に付着しており、棘下筋と共に腕を外向きにひねる役割を果たす。
大円筋(だいえんきん)
大円筋は腕を体に向かって引き寄せ、体内に回転させます。また、大円筋は腕を後ろに動かす動作も行います。
前鋸筋(ぜんきょきん)
前鋸筋は、肩甲骨の前方への移動と上方への回転を助け、肩関節の可動域を広げる役割を持っています。
肩甲下筋(けんこうかきん)
肩甲骨の裏側から上腕骨に付着しており、腕を内向きにひねる役割を果たします。
大胸筋(だいきょうきん)
大胸筋は、胸の前面に位置しており、鎖骨・胸肋・腹部から上腕骨までの幅広い位置に付着しています。動きとしては、前方へ腕を伸ばす、押し出す動きです。
肩の疾患
肩の疾患については以下のようなものになります。
・腱板損傷・腱板断裂
・肩関節拘縮、凍結肩(四十肩・五十肩)
・変形性肩関節症
・肩関節インピンジメント症候群
・石灰沈着性腱板炎
などがありますが、当院に来られる方の中でもっとも多い疾患は肩関節拘縮、凍結肩(四十肩・五十肩)です。
・腱板損傷・腱板断裂
腱板は肩関節を安定させ動かすために重要なもので、40代頃から腱の老化が起き、腱板の強度が低下し断裂の危険性が高まります。転倒・打撲などの外傷で起きるものもあり、日常的に肩をよく使う方や力仕事を繰り返している方に比較的多く外傷によるものは転倒して手や肘をついたり、重いものを持ち上げたり肩を捻ったりして発症する場合もあります。
・肩関節拘縮、凍結肩(四十肩・五十肩)
肩関節拘縮とは、 いわゆる四十肩・五十肩と呼ばれる肩関節の炎症によるもので、転倒や打撲後の不動が原因で二次的に起こるものがあり、場合によっては痛みを伴います。
・変形性肩関節症
肩関節内の軟骨がすり減ることで、肩の動きが悪くなり、音がゴリゴリと鳴ったり、肩を動かそうとすると痛む、腕がスムーズに挙げれないなどの症状が起きます。これらの症状がある場合は、肩の骨が変形している「変形性肩関節症」という病気が考えられる。
・肩関節インピンジメント症候群
インピンジメント症候群とは、肩の関節にある骨と骨の間が狭くなり、腕を動かすときに肩の腱や筋肉が擦れたり、挟まれたりすることで痛みや炎症を引き起こす肩関節の疾患です。インピンジメント症候群の原因は、加齢による肩関節周りの筋肉の衰え、日常的な姿勢が悪くなることで肩関節の隙間が狭くなること、スポーツや仕事などで肩を酷使することで起きてしまうことが挙げられます。
・石灰沈着性腱板炎
石灰沈着性腱板炎とは、肩の安定性に必要な腱板に、カルシウムの結晶である石灰が溜まる疾患です。30~60歳くらいの年代での発症が多く、やや女性の罹患率が高いものです。 はっきりとした原因の分からない疾患ですが、多くは短期間で自然に軽快し、もう一方で、長期間痛みに悩まされている方もいます。
病院などが肩に対して行う治療
腱板断裂・腱板損傷
腱板断裂・腱板損傷の病院での治療は保存療法と手術療法の2つの治療法があります。保存療法として、急性外傷で始まった時は、三角巾で肩を固定して1~2週安静にします。断裂した部分が治癒することはありませんが、保存療法である程度軽快します。保存療法では、薬や注射療法と運動療法が行なわれます。薬の服用や湿布薬で痛みを和らげたり、強い痛みに対してはヒアルロン酸やステロイドの注射療法を行います。薬や注射で痛みが軽減したら、リハビリで肩関節の拘縮を防ぎ、損傷せずに残っている腱板での機能改善を目指します。
リハビリでは肩周りの筋肉のストレッチを行い、可能な場合はゴムチューブを用いたトレーニングなどで、肩を挙げやすい状態にします。
保存療法で肩関節痛と運動障害が治らないときは、手術を行ないます。
手術には、関節鏡視下手術と通常手術(直視下手術)があります。
関節鏡視下手術の方が低侵襲で、手術後の痛みが少ないので、普及してきていますが、大きな断裂では、縫合が難しいので、直視下手術を選択するほうが無難です。どちらの手術も、手術後は、約4週間の固定と2~3ヵ月の機能訓練が必要です。
肩関節拘縮(四十肩・五十肩)
自然に治癒することもありますが、軽い痛みだからと放置してしまうと日常生活に支障が出るだけじゃなく、肩関節が癒着をして腕が動かせなくなることもあります。痛みが強い急性期には、三角巾での肩の固定をして安静を計り、消炎鎮痛剤の内服、注射を打つのが良好です。急性期を過ぎ痛みが落ち着いてきたら、温熱療法(ホットパック、入浴など)や運動療法(拘縮予防や筋肉の強化)などのリハビリを行います。これらの方法で改善しない場合は、手術を勧めることもあります。
変形性肩関節症
痛みや可動域の制限に対しては、まずは飲み薬を服用して痛みを和らげて、ストレッチや筋力トレーニングなどのリハビリを行い肩の可動域を拡げていきます。肩の炎症がひどく痛みが強い場合には、ステロイドを使用した関節注射が行われることもあります。関節の変形が進行して痛みや動きの制限が日常生活に支障をきたす場合には、人工肩関節置換術が標準的な治療法とされています。
変形性肩関節症を予防するためには、適度な運動(ウォーキングや水泳など、関節に負担をかけない運動)や正しい姿勢を取ることが大事で、猫背など悪い姿勢は肩に負担をかけるため正しい姿勢を心がけます。
肩関節インピンジメント症候群
安静時や夜間の痛みに対して、消炎鎮痛薬を使用したり、局所麻酔薬とステロイドの肩峰下滑液包への注射を行います。投球動作を伴うスポーツなどはしばらく中止しておくのが良いです。リハビリは特に有効な保存治療で、肩関節腱板の強化訓練によって炎症を抑制し、機能低下を防ぐことができます。炎症がある場合では、痛みの軽減を最優先にし、肩関節に過度な刺激を与えず避けることが大切です。疼痛が強い急性期では肩を無理に動かすことにより疼痛が強くなってしまうため注意が必要です。特に中高年では肩関節、肩甲骨の動きが悪くなっていることが多い。したがって肩の動きだけではなく、肩甲骨などの柔軟性に問題がないか確認してストレッチすることが重要です。リハビリによって肩関節の機能を回復できても、炎症が治まりきらず痛みがあまり減らない状態の場合には手術適応の可能性もあります。
石灰沈着性腱板炎
石灰沈着性腱板炎の治療はまず保存療法から始めていきます。保存療法には、痛みを和らげるために痛み止めの内服や、痛みが楽になってきた時には肩の動きを改善するためリハビリテーションを行います。しかし鎮痛剤は、痛みを軽くするための薬で、石灰沈着性腱板炎そのものの病気を治す治療ではありません。また激痛の時には肩周りのマッサージやストレッチも炎症がひどくなるだけなのでNGです。保存療法が効果がない場合、注射療法による局所麻酔薬やステロイド注射を行います。炎症を直接抑えることができる有効な方法で、石灰沈着した部位へ正確に注射することが重要です。また石灰を吸引することで石灰が消失することも可能です。注射療法は、短期間で痛みを和らげることができます。その他として体外衝撃波治療があり、カルシウム沈着物を破壊し、痛みを軽減するため治療法があります。この治療法は、尿管結石に行う体外衝撃波治療と原理は同じで、石灰沈着性腱板炎に対して非常に効果的であります。衝撃波を利用してカルシウムを分解し、炎症を抑える効果があり、治療は数回のセッションで行われ痛みの軽減や肩の可動域の改善が期待できます。保存療法や注射療法、体外衝撃波治療でも改善しない場合、手術が検討されます。
上記のように症状によって病院の対応は色々あります。ですがそのすべてによって症状が良くなるわけではありません、病院でうまくいかなかった場合などどうしようもなくなった際に当院の施術も改善方法の1つと覚えておいてください。
当院での肩の痛みに対する改善法
では当院では肩の痛みに対してどんな改善法なのかというと、
・話を聞く
・身体のバランスを診る
・歩行を診る
・どんな状態なのかの説明
・施術
話を聞く
なぜ今の身体になったのか時系列で導き出していき、どのくらいの期間悪くなってどこに負担をかけているのか、普段どんな姿勢で生活や仕事をしているのかを聞きます。正直いって腰痛にも十人十色あり同じ治療なんてありません、ですから決まったマッサージやストレッチで良くならないんです。
バランスを診る
それから身体のバランスを見ます、左右のバランスが崩れていることは当然負担になっているはずです。
歩行を診る
そして歩行を見ます、これも歩き方によって常日頃からかばって歩いていたり知らず知らずに悪い方向へ行っていることもあります。
どんな状態なのかの説明
これはすごく大事なことでご自身の大事な身体が今どうなっているのかを知ってもらうことです。そうすることで何をしていかないといけないのかなど明確になって身体の改善に向かうことができます。
施術
どんな施術かというと伝えにくいですがまず当院の施術はソフトです、よく施術を受けられた方に「めちゃくちゃやさしいですね」「眠くなります」「気持ちがいい」などのお声を頂ける一方で「これで大丈夫なのかな」などの声もお聞きします、正直お身体を改善に導くのに強い力は必要なりません。
寝返り動作がきついならその動作の改善、腕を上げる動作がきついならその動作の改善、腕を後ろに回す動作がきついならその改善という考えの元で施術をしておりますので一人一人オーダーメイドの施術となっております。ですので初回は問診から施術までの時間が1時間から1時間半くらいはかかってしまうため、「話はいらないから早く治療してくれ」「説明はいらない」など思われる方は当院の施術には向かないためご遠慮下さい。逆にしっかり自分の身体を知っておきたい、良くしたいという方は↓からご予約お待ちしております。